どーも、ききです。
今回は危険物乙1.2類の「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」攻略について解説します。
はじめに
まず、今回の解説は個別に受験する場合よりも、どちらかと言うと甲種受験の為の解説となります。
こちらの記事で解説していますが、先に乙種3.4.5.6類を取得している方を前提に話を進めていきます。
仮に乙3.4.5.6類を持っている状態ならば、あとは「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」については乙1.2類だけ覚えるだけでいいのです。
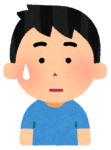
って言っても他の乙類はほとんど忘れてる…
そのような方の為に乙3.4.5.6類は個別に解説しているので、こちらをご覧ください。
※人によっては乙1.3.4.5類で取得してから甲種を受験される場合もあると思いますが、そのような方でも復習も兼ねてご覧下さい。
甲種受験では他に「物理・化学」と「法令」についても問われますが、長くなるので今回は「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」だけについて解説していきます。
ちなみに個別に乙1.2類を受験する方でも役に立つと思いますので、活用して下さい。
※乙4類に関しては恐らく先に取得している方が大半だと思うので、割愛します。
機会があれば乙4類についても解説しますが、乙4類に限っては非常に多くのサイトやブログで解説されているので、敢えてこのブログで解説する必要はないかと思います。
もし、希望があれば解説します(ない
※追記 乙4の記事公開しました。
第1類に共通する特性
まず全体の共通点について解説します(特に重要な部分は赤字で表示しています)
- 第1類は酸化性の固体
- 大半は無色の結晶か白色の粉末
- 不燃性(無機化合物)
- アルカリ金属の過酸化物は水と反応すると酸素を発生させる
- 比重は1より大きく、水に溶けるものが多い
貯蔵時の注意点として
- 加熱、衝撃、摩擦など避けて貯蔵
- アルカリ過酸化物は水との接触を避ける
- 容器は密栓
- 潮解しやすいものは湿気に注意
消火時する際は大量の水で冷却するのが大半ですが、アルカリ過酸化物は水を掛けるとマズいので炭酸水素塩類の粉末消火器や乾燥砂で消火します。
つまり、アルカリ過酸化物とそれ以外で大きく性質が異なる事が分かります。
第1類、個別の特性
第1類は品名が10種類あります。
- 塩素酸塩類
- 過塩素酸塩類
- 無機過酸化物
- 亜塩素酸塩類
- 臭素酸塩類
- 硝酸塩類
- ヨウ素酸塩類
- 過マンガン酸塩類
- 重クロム酸塩類
- その他
それぞれ個別に物質が存在しますが、非常に量が多いので、覚える必要があるものをピックアップしていきます(それでも多いですが
†塩素酸塩類†
- 無色の結晶又は白色の粉末
- 熱湯に溶ける
- 強力な酸化剤で有毒
- アンモニアとの反応生成物は自然爆発する可能性あり
- アルコールには溶けない
- 潮解性なし
- 無色の結晶
- 潮解性有り
- アルコールに溶ける
- 無色の結晶
- 常温でも爆発の危険有り
- アルコールには溶けにくい
次の過塩素酸塩類は実はほとんど塩素酸塩類と同じです。
過塩素酸塩類は過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムとありますが、あまり覚えなくてもいいと思います(試験に出たら大体同じって事を思い出して下さい
†無機過酸化物†
最初の解説で水を掛けるとヤバいと書いていたのは、この無機過酸化物の事です。
つまり、第1類ではこの無機過酸化物以外は全て水を掛けて消火します。
- オレンジ色の粉末
- 水と反応して発熱、酸素と水酸化カリウムを発生
- 吸湿性が強く、潮解性有り
- 黄白色の粉末
- 水と反応して発熱、酸素と水酸化ナトリウムを発生
- 吸湿性が強い
この2種類はアルカリ金属。
- 無色の粉末
- アルコール、エーテルには溶けないが酸には溶ける
- 無色の粉末
- 加熱すると酸素と酸化マグネシウムを発生
- 灰白色の粉末
- 酸か熱湯に反応して酸素を発生
この3種類はアルカリ土類金属。
†亜塩素酸塩類†
- 白色の結晶
- 吸湿性有り
- 無機酸、有機酸とも反応する
- 直射日光や紫外線で分解するので、直射日光を避けて冷暗所に貯蔵
†臭素酸塩類†
- 無色の粉末
- アルコールには溶けにくい
†硝酸塩類†
- 無色の結晶
- 単独でも加熱で分解し酸素を発生
- 無色の結晶
- 潮解性有り
- 白色の結晶
- 別名硝安と呼ばれる
- 吸湿性、潮解性有り
- 単独でも加熱や衝撃により爆発する事がある
- 210℃で亜酸化窒素が発生
- アルカリと接触するとアンモニアを発生
- 水に溶ける際、激しく吸熱
- アルコールに溶ける
†ヨウ素酸塩類†
- 白色の結晶
- アルコールには溶けない
- 無色の結晶
- アルコールには溶けない
†過マンガン酸塩類†
- 赤紫の結晶
- 硫酸を加えると爆発
- 塩酸と接触すると塩素、アルカリと接触すると酸素を発生
- 水に溶けると濃紫色になる
- アルコールやアセトンに溶ける
- 赤紫の粉末
- 潮解性有り
- 硫酸を加えると爆発する
†重クロム酸塩類†
- 橙赤色の結晶
- エタノールには溶けない
- 毒性が強い
- 橙赤色の結晶
- 毒性が強い
- エタノールに溶ける
- 加熱すると窒素を発生(同時に酸素も発生)
†その他†
- 白色の粉末
- 加熱により酸素を発生
- 暗赤色の結晶
- エタノール、エーテルに溶ける
- アルコール、エーテル、アセトンなどと接触すると発火
- 水と接触すると発熱
- 酸化性が強い
- 潮解性有り
- 暗褐色の粉末
- 水、アルコールに溶けない
- 日光が当たると酸素を発生
- 有毒
- 電気の良導体
- 水と反応して塩化水素を発生
- 吸湿性有り
- 光や熱により分解
- 別名高度さらし粉
- アンモニアと混合すると爆発
軽く重点をまとめると
似たような名前が多いので混乱しますが、それぞれの色やアルコールなどに溶けるなどの特徴は押さえておきましょう。
とりあえず、1類はほとんど酸素を発生すると覚えておけば「水素が発生する」みたいな問題はすぐに謝りと判断出来ます。
第2類に共通する特性
乙類の中では一番不遇の扱いな乙2類。
この乙2類は個別に必要な人以外はまず個別に取得することがない資格です。
甲種受験で乙種を4種類取得する場合、
- 第1類or第6類
- 第2類or第4類
- 第3類
- 第5類
となっていて、乙3.5類は確定として恐らく大多数の方は事前に乙4類を持っている状態だと思います(第1類と第6類は個人差有)
従って、本当に必要な方か甲種を目指す方以外まず取得する事がない資格となっています(若しくは乙類全制覇を目指す猛者くらいでしょうか)
こちらもまず、全体の共通点について解説します(特に重要な部分は赤字で表示しています)
- 固体の可燃性物質
- 一般に比重は1以上
- 一般に水には溶けない
- 酸化されやすい物質
- 酸化剤と混合すると発火、爆発する恐れ有り
- 火気や高温体、加熱を避ける
- 酸化剤との接触を避ける
- 防湿し容器は全て密栓
- 消火方法は水系の消火器で冷却消火or乾燥砂などでの窒息消火
第2類、個別の特性
第2類の品名は大きく分けて7種類あります。
- 硫化リン
- 赤リン
- 硫黄
- 鉄粉
- 金属粉
- マグネシウム
- 引火性固体
†硫化リン†
- それぞれ融点は173℃、290℃、310℃
- 黄色または淡黄色の結晶
- 燃焼すると有毒ガスを発生
- 二硫化炭素に溶ける
- 三硫化リンは熱湯、五硫化リンは水、七硫化リンはどちらにも反応し硫化水素を発生
- 消火時は水は厳禁、乾燥砂で窒息消火
- 火気、加熱、酸化剤、水、金属粉と接触しないように貯蔵
†赤リン†
- 赤褐色の粉末
- 無臭で無毒
- 水にも二硫化炭素にも溶けない
- 赤リン自体は黄リンより安全
- 自然発火はしないが、黄リンを含んだものは自然発火の可能性有り
- 燃焼すると有毒なリン酸化物が発生
- 注水か乾燥砂で消火
†硫黄†
- 融点は115℃
- 黄色の固体、または粉末
- 水には溶けないが二硫化炭素には溶ける
- 燃焼すると二酸化硫黄を発生
- 電気の不良導体で静電気を発生しやすい
- 空気中に飛散すると粉塵爆発する危険有り
- 水と土砂で消火する
†鉄粉†
- 灰白色の粉末
- 水、アルカリには溶けない
- 酸に溶けて水素を発生
- 油のしみこんだものは自然発火する恐れ有り
- 微粉状のものは粉塵爆発する恐れ有り
- 酸化剤が混合したものは加熱や衝撃により爆発する恐れ有り
- 湿気により酸化、発火する恐れ有り
- 加熱により発火する恐れ有り
- 消火の際は注水は厳禁、乾燥砂による窒息消火
†金属粉†
- 銀白色の粉末
- 燃焼すると酸化アルミニウムを発生
- 水には溶けないが酸やアルカリに溶けて水素を発生
- 空気中の水分やハロゲン元素と反応して自然発火する恐れ有り
- 酸化剤と混合したものは加熱、衝撃により発火する恐れ有り
- 微粉状のものは粉塵爆発する恐れ有り
- 水分やハロゲンとの接触をさけて貯蔵
- 消火に注水は厳禁、乾燥砂で窒息消火
- 灰青色の粉末
- 硫黄と混合したものを加熱すると硫化亜鉛を発生
- 貯蔵、消火の方法はアルミニウム粉と同じ
- 重金属
†マグネシウム†
- 銀白色の軽い金属
- 水には溶けずアルカリと反応しないが、酸に反応し水素を発生
- 常温では酸化被膜が生成されているので安定している
- 冷水には徐々に、熱湯には激しく反応して水素を発生
- 空気中の水分と反応して自然発火する恐れ有り
- 酸化剤と混合したものは加熱、衝撃により発火する恐れ有り
- 燃焼すると酸化マグネシウムを発生
- 水分や酸との接触を避けて貯蔵
- 消火では注水は厳禁、乾燥砂による窒息消火
†引火性固体†
固形アルコール、その他1気圧において引火点が40℃未満のものをいい、常温で可燃性蒸気を発生するので、常温でも引火する危険性の高い物質です。
- 乳白色の寒天状
- メタノール、エタノールを凝固剤で固めたもの
- 40℃未満で可燃性蒸気を発生
- 臭気有り
- のり状の固体
- 生ゴムを溶かした接着剤
- 引火点が10℃以下なので、常温以下の温度で引火性蒸気を発生
- 水には溶けない
- 直射日光を避ける
- ペースト状の固体
- トルエン、酢酸ブチル、ブタノールなどを成分とした下地修正塗料
- 蒸気を吸引すると有機溶剤中毒になる恐れ有り
- 直射日光を避ける
重点をまとめると
- 固形アルコール以外比重は1以上
- 水には溶けない
- 二硫化炭素に溶けるものは硫化リンと硫黄
- 自然発火の恐れがあるものは赤リン(硫黄を含むもの)、鉄粉、アルミニウム粉、亜鉛粉、マグネシウム
- 鉄粉とマグネシウムは酸と反応して水素を発生。アルカリとは反応しない。
- アルミニウムと亜鉛は酸とアルカリに反応して水素を発生。
- 水と反応して硫化水素を発生するものは硫化リン
- 加熱して二酸化硫黄を発生するものは硫化リン、硫黄
- 赤リン、硫黄、引火性固体以外に注水は厳禁
最後に
今回は過去問の解説など行いませんでしたが、基本的に暗記まみれの資格なので試験前の確認にご利用下さい。
今回参考にしたテキストはこの2冊になります。
この弘文社の参考書は恐らく甲種受験を目指す人は、ほとんどこの参考書を読んでいると思います。
それくらい有名で「合格する為に必要な知識が詰まっている」ので、受験される方にはオススメの一冊です。
こちらに危険物甲種の攻略記事をまとめていますので、受験される方は参考に下さい。
今回はこの辺で…

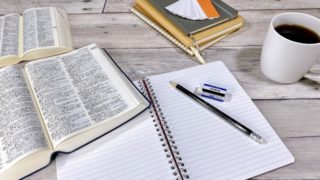




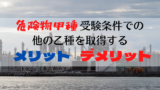
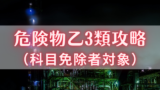


-160x90.png)
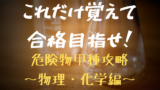


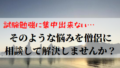
コメント
こんにちは、以前高圧ガス丙種化学の時にお世話になった者です。コチラのブログで勉強させて頂き、お陰様で合格できました\(^o^)/
今度は乙2取ってこいと会社から仰せつかり、KiKiさんのブログを思い出して、覗かせて頂いております。
初心者でも理解しやすい内容で、大変助かります。嫌な勉強ですが、今回もブログを楽しみながら頑張れそうです( ^ω^ )
コメントありがとうございます。高圧ガスもお疲れ様でした。乙2に関しては自分は個別には取得していませんが、甲種受験の際に学習した事をブログでまとめています。このようなコメントを頂くと泣く程嬉しいです!ありがとうございます!
最終的に甲種を目指すのであればそちらも記事を書いているので是非参考にしてみて下さい。
KIKIさんの解説めちゃくちゃわかりやすいです。。。
できれば乙4の解説も載せてほしいです、、、(泣)
コメントありがとうございます。甲種受けるには乙4も復習が必要ですよね…ちょっと時間掛かりますが、記事作成進めていきます!