どーも、ききです。
今回は危険物乙5類の攻略記事です。
前回の乙3類の続きで乙5類も自力で甲種取得する方の必須の科目になっています。
これから受験される方対象に攻略を書いていますので今後受けられる方は是非参考にして下さい。
危険物乙5類とは

危険物取扱者の資格の詳細と他の乙類の攻略は以前の記事をご覧下さい。
危険物乙5種はほとんど聞いた事がない危険物が対象です。この危険物を取り扱う会社以外でほぼ必要ない資格でこれを受験する人は恐らく甲種受験の為だと思います。
聞いた事がない危険物ばかりなので、1から覚える事が多いです。なので他の危険物と同時に受験する方は乙5種の勉強量を少し多めに確保する事をおススメします。
今回も前回同様に試験に出てきそうな箇所だけ厳選してまとめていきます。受験する時の参考にして下さい。
第5類危険物に共通する特性
5種の危険物は自己反応性を有する、液体または固体です。
共通する性質として
- 全て比重は1以上
- 燃えやすく燃焼速度が速い
- 内部に酸素と可燃物を有している為、酸素供給源ななくても燃焼する
- 一部を除いて基本的に容器は密栓して通風の良い冷暗所に貯蔵する
- 一部を除いて消火に関しては大量に水を注水する
- 危険物の量が多い場合や広がった時は消火は困難
- 空気中にしばらく放置すると分解し自然発火するものがある
3類の乾燥砂を使った窒息消火は5類ではほとんど通用しません。代わりに水での消火が有効な場合が多いので覚えておきましょう。
次からは個別の危険物について解説します。
第5類危険物、個別の特性
こちらも覚えたほうがいい箇所だけ解説していきます。特に覚えた方が良い所は赤字になっています。もっと深く知りたい時は参考書などを参考にして下さい。多分そこまで深く覚えなくても合格ラインは問題ないかと思います。
ちょっと名前が長くて覚えずらいですが、自分の場合長い名前は最初と最後で繋げて覚えました(ジニトロソベンタメチレンテトラミン=ジニミンみたいに)
なので自分なりに覚えやすい方法を探してみてください。念のため自分で略した名前も記載していきます(名前の横にカッコで記載します)
赤字は重要なところで赤太字は絶対覚えて下さい。
- 白色の固体
- 無臭
- 有機溶剤に溶ける
- 強い酸化作用
- 100℃で分解して白煙を発する
- 直射日光、乾燥状態は厳禁
- 無色透明の液体
- 独特の臭い
- ジエチルエーテルに溶ける
- 強い酸化作用
- 40℃で分解が促進
- 直射日光、乾燥状態は厳禁
- 容器は密栓せず、通気性のあるものを使用
- 無色透明の液体
- 強い刺激臭
- 水、アルコール、エーテル、硫酸に溶ける
- 強い酸化作用
- 110℃で発火し爆発する
- 直射日光、乾燥状態は厳禁
- 無色透明の液体
- 有機溶剤に溶ける
- 引火性有り
- 芳香、甘味がある
- 直射日光は厳禁
- 無色の油状の液体
- 有機溶剤に溶ける
- 甘味があり有毒
- 周囲のものを汚した時は苛性ソーダのアルコール溶液を注いで分解しふき取る
- 無味、無臭
- 有機溶剤に溶ける
- 乾燥状態は厳禁。エタノールか水で湿綿して保存
- 安定度試験を定期的に行い、耐熱度が低下したものは安全な方法で処理する
- 黄色の結晶
- 無臭で苦味、有毒
- 熱湯、アルコール、ジエチルエーテル、ベンゼンに溶ける
- 金属と乾燥状態は厳禁
- 淡黄色の結晶
- アルコールは熱すると溶け、ジエチルエーテルに溶ける
- 日光に当たると茶褐色に変わる
- 固体より溶融したものの方が危険
- 淡黄色の粉末
- 液性は中性
- 水、ベンゼン、アルコール、アセトンにわずかに溶ける
- 酸、有機物との接触を避ける
- 白色の粉末
- 融点以上に加熱すると、窒素とシアンガスが発生
- アルコール、エーテルに溶ける
- 直射日光は厳禁
- 黄色の粉末
- アセトンに溶ける
- 光によって褐色に変化
- 水かアルコールの混合液の中で保存
- 白色の結晶
- 温水に溶けて酸性を示す
- 還元性が強い
- 直射日光、酸化剤、アルカリ、可燃物は厳禁
- 白色の結晶
- 水、アルコールに溶ける
- 還元性が強い
- 乾燥した冷暗所に貯蔵
- 白色の結晶
- 水に溶けて、アルコールに溶けない
- 強い還元性
- 水溶液は金属を腐食
- 乾燥した冷暗所に貯蔵
- 基本的には上記の硫酸ヒドロと同じで115℃以上に加熱すると爆発する可能性がある
- 無色の結晶
- 水に溶けるがエタノールに溶けにくくエーテルには解けない
- 直射日光、酸、金属は厳禁
- 消火時水は厳禁
- 白色の結晶
- 水、アルコールに溶ける
- 有機物や還元性物質との接触を避ける
ここで性質別に分別していきます。
直射日光が厳禁なのは
過酸化ベンゾイル、メチルエチルケトンパーオキサイド、過酢酸、硝酸エチル、硝酸メチル、アゾビスイソブチオニトリル、硫酸ヒドラジン、アジ化ナトリウム
乾燥状態が厳禁なのは
過酸化ベンゾイル、メチルエチルケトンパーオキサイド、過酢酸、ニトロセルロース、ピクリン酸、ジアゾジニトロフェノール
逆に乾燥状態にしなければいけないのは
ヒドロキシルアミン、硫酸ヒドロキシルアミン、塩酸ヒドロキシルアミン(ヒドロ3兄弟)
水に溶けるのは(わずかに溶けるは入れていません)
過酢酸、ヒドロキシルアミン、硫酸ヒドロキシルアミン、塩酸ヒドロキシルアミン、硝酸グアニジン(一応アジ化ナトリウムも水に溶けますが危険)
温水、熱湯に溶けるのは
硫酸ヒドラジン、ピクリン酸
引火性があるものは
硝酸エチル、硝酸メチル、ピクリン酸、過酢酸、エチルメチルケトンパーオキサイド
消火時に乾燥砂を使用するのは
アジ化ナトリウム
基本的に消火は困難な危険物ですが、大半は注水による冷却消火が有効です。
全体的に直射日光と乾燥状態が厳禁なものが多いですが、逆に乾燥状態にしなければいけないものがあるのでそこは個別に覚えましょう。
過去問解説
消防試験研究センターには過去に出題した問題という事で危険物全種の問題が掲載されています。
例の如く解説が一切掲載されていないので、こちらでは簡単な解説も含めて紹介します(本当に簡単な解説)
試験前の仕上げに一度目を通しておきましょう。
危険物の類ごとの性状について、次のA~Eのうち誤っているものはいくつあるか。
A 第1類の危険物は、酸素を含有しているため、加熱すると単独でも爆発的に燃焼する。
B 第2類の危険物は、いずれも固体の無機物質で、酸化剤と接触または混合すると衝撃等により爆発する危険性がある。
C 第3類の危険物は、いずれも自然発火性物質および禁水性物質の両方の危険性を有する物質である。
D 第4類の危険物は、炭素と水素からなる化合物で、一般に、蒸気は空気より重く低所に流れ、火源があれば引火する危険性がある。
E 第6類の危険物は、酸化力が強く、自らは不燃性であるが、有機物と混ぜるとこれを酸化させ、着火させることがある。
答えは4つです。
一問目は得意のそれぞれの特徴を問う問題が出ます。
最低限覚えておかなければいけないのは
1類…酸化性固体(不燃性)
2類…引火性固体(可燃性)
3類…自然発火性および禁水性の固体又は液体(ほとんど可燃性で一部不燃性有)
4類…引火性液体(可燃性)
5類…自己反応性固体又は液体(可燃性)
6類…酸化性液体(不燃性)
第5類の危険物(金属のアジ化物を除く)の火災に共通して消火効果が期待できるものは、次のうちどれか。
1. リン酸塩類の消火粉末を放射して消火する。
2. 炭酸水素塩類の消火粉末を放射して消火する。
3. 棒状または霧状の水を大量に放射して消火する。
4. 二酸化炭素を放射して消火する。
5. ハロゲン化物を放射して消火する。
答えは3です。
5類は基本的に注水での消火ですが、アジ化ナトリウムだけ水は厳禁です。
過酸化ベンゾイルの貯蔵、取扱いについて、次のうち誤っているものはどれか。
1. 日光により分解が促進されるため、直射日光を避ける。
2. 水と徐々に反応して酸素を発生するため、乾燥状態にする。
3. 衝撃に対し敏感で爆発しやすいため、振動や衝撃を与えない。
4. 火炎の接近により急激に燃えるおそれがあるため、火気厳禁とする。
5. 加熱すると分解し爆発するおそれがあるため、加熱を避ける。
答えは2です。
過酸化ベンゾイルは良く特徴を問う問題が出るのでしっかり特徴を押さえておきましょう。
第5類の危険物に共通する貯蔵および取り扱い方法について、次のうち誤っているものはどれか。
1. 他の薬品と接触させない。
2. 固体のものは、すべて乾燥を保つ。
3. 衝撃、摩擦を避ける。
4. 火気、加熱を避ける。
5. 通風のよい冷所に貯蔵する。
答えは2です。
乾燥状態が危険なものと乾燥状態にしなければいけないものの違いをしっかり把握しておきましょう。
過酢酸の貯蔵、取扱いの方法として、次のうち適切でないものはどれか。
1. 熱源や火源と接触させないように取り扱う。
2. 容器は、密封して換気良好な冷暗所に貯蔵する。
3. 衝撃や摩擦を受けないように取り扱う。
4. 安定剤として、アルカリ剤を混合して貯蔵する。
5. 使用した容器等は、完全に洗浄する。
答えは4です。
過酢酸の特徴もしっかり押さえておきましょう。
第5類の危険物の性状について、次のうち誤っているものはどれか。
1. 酸素を含み自己反応性を有するものが多い。
2. 加熱、衝撃、摩擦等により発火するおそれはない。
3. 空気中に長時間放置すると分解が進み、自然発火するものがある。
4. 燃焼速度が大きい。
5. 重金属と作用して爆発性の金属塩を形成するものがある。
答えは2です。
5類は加熱等により爆発する危険性があります。覚えておきましょう。
第5類の有機過酸化物の性状等について、次のうち誤っているものはどれか。
1. 固体または液体である。
2. 結合力が比較的弱い酸素・酸素結合(―O―O―)を分子中に有する化合物である。
3. 熱、光あるいは還元物質により容易に分解し、遊離ラジカルを発生する。
4. 金属塩や塩基類などが混入すると、反応性が高まるものがある。
5. 自己反応性は強いが、衝撃や摩擦等に対しては安定である。
答えは5です。
有機過酸化物は自己反応性が強く、衝撃や摩擦等にも反応します。
ニトロセルロースの性状について、次のうち誤っているものはどれか。
1. 日光の直射により分解し、自然発火することがある。
2. 含有窒素量(硝化度)の多いものほど危険性は大きくなる。
3. エタノールや水に溶けやすい。
4. 燃焼が極めて速い。
5. 乾燥状態で貯蔵すると危険である。
答えは3です。
ニトロセルロースは、エタノールやアセトンなど有機溶剤には溶けますが、水には溶けません。
ジアゾジニトロフィノールの性状について、次のうち誤っているものはどれか。
1. 黄色の粉末である。
2. 光により変色する。
3. 水よりも重い。
4. 加熱により融解して安定化する。
5. 摩擦や衝撃により爆発する。
答えは4です。
ジアゾジニトロフェノールは、加熱すると分解して爆発することがあります。
最後に
乙5種はホント意味不明な名前が多く覚えるのに苦労しますが、自分なりに少しでも覚えやすく改名(?)するのが速く覚える為の攻略です。
あとはヒドロ3兄弟のように大体同じような名前は同じような性質なので覚える時の参考にして下さい。
では今回はこの辺で
今回参考にしたテキストは乙3種と同じものです。他の乙種もこれ一冊でテキストと問題集で繰り返し勉強出来るのでオススメです(科目免除者限定です)
あとは過去問をじっくり解いて試験に臨みましょう!
また、こちらに危険物甲種の攻略記事をまとめていますので、受験される方は参考にしてみて下さい。
今回はこの辺で…

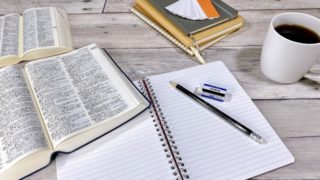





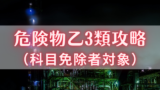

-160x90.png)
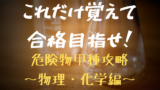

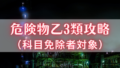
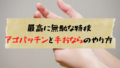
コメント